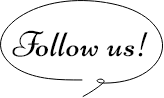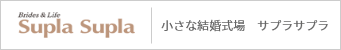七五三 ルールとマナー徹底解説

七五三に込められた意味やお祝いの方法・マナー
目次
七五三とは?子どもの成長を願う日本の大切な行事
秋になると、晴れ着を身にまとった子どもたちとご家族が、神社へお参りする光景を目にするようになります。
この風習は「七五三(しちごさん)」と呼ばれる、日本ならではの大切なお祝いです。

けれども、なぜ3歳・5歳・7歳の年にお祝いをするのか、どのような意味があるのかをご存じでしょうか?
また、着物を着る理由や、昔と今でどう変わってきたのかも、意外と知られていないかもしれません。
この文章では、七五三の由来や年齢ごとの意味、そしてお祝いに用いられる衣装の背景まで、わかりやすくご紹介いたします。
・七五三は「成長の節目」を祝う行事
七五三とは、子どもが健康に育ってきたことへの感謝と、これからの無事を願うための行事です。
この風習の始まりはとても古く、平安時代までさかのぼります。
もともとは公家や武家の家で行われていた成長の儀式が、江戸時代に庶民の間にも広まり、明治時代に現在のような形式として整えられました。
戦後には全国的に広く行われるようになり、現代でも続いている大切な風習です。
・なぜ「3歳・5歳・7歳」で祝うのか?
年齢|儀式の名前|意味
3歳|髪置(かみおき)の儀|それまで剃っていた髪を、伸ばし始める節目。
髪は命の象徴とされ、健康を願う意味があります。
5歳|袴着(はかまぎ)の儀|初めて袴をはくことで、男の子が社会の一員として歩み始めるとされる儀式です。
7歳|帯解(おびとき)の儀|女の子が紐付きの子ども用着物から、帯を使った着物に変えることで、少女から女性への一歩を表します。

・お祝いの日は?
時代とともに変化七五三のお参りは、一般的に11月15日に行われますが、地方によっては外でも過ごしやすくなる10月中旬頃から神社参拝を行うご家庭が多く、寒さが早く訪れる地域では、雪や寒さが強くなる時期をさけるために早めに行うご家庭も多く見られます。
最近では、日付などに厳重な決まりはなく、お参り・食事・記念撮影などを別々の日に分けることで、1日のスケジュールにゆとりをもって祝う方法も一般的になってきました。
七五三の衣装に込められた意味とは?七五三といえば、やはり着物姿が印象的ですが、それぞれの年齢ごとに着るものが違うのをご存じでしょうか。
3歳、5歳、7歳それぞれの衣装にも、七五三の由来や願いが深く関わっているので確認してみましょう。
〇3歳の七五三3歳の七五三は「髪置の儀」がもとになっています。
3歳のお子さまの場合はまだ身体が小さく、長時間の着物が負担になることもあります。
そこで、やわらかな被布(着物の上に羽織る上着)が選ばれることが多く、見た目もあどけなさがある3歳のお子さまには可愛らしい印象になります。
最近では、お子さまの負担を少なくするために、動きやすい洋服でのお祝いも増えています。
ワンピースやスーツといった正装であれば、着物でなくても十分です。

男の子…着物・羽織・袴の三点もしくは被布スタイル
女の子…被布を着るスタイルが一般的です。
〇5歳の七五三5歳の男の子は「袴着の儀」がもとになっており、初めて袴を着ることが大きな意味を持ちます。
男の子らしい凛とした姿に、親としての喜びもひとしおです。

男の子…着物・羽織・袴の三点に加え、小物類(懐剣や扇子など)もあると良いでしょう。
女の子…被布スタイルや着物に袴を合わせる着方でも問題ありません。
〇7歳の七五三7歳の女の子は「帯解の儀」がもとになっています。
それまでは紐で留める子ども用の着物を着ていましたが、この年齢から大人と同じように帯を締めるようになります。
帯を使った着物は、見た目がより華やかになるだけでなく、幼女から少女へと「大人への第一歩」を象徴する大切な装いとなっています。

女の子…着物、帯、髪飾りなど。その他にも扇子や箱迫、伊達締め、バッグなど7歳の女の子は七五三の中で一番用意をするものが多いです。
男の子…5歳と同じ羽織袴が一般的です。
・ 和装だけでなく洋装でも大丈夫七五三の服装には「これでなければならない」という決まりはありません。
和装が伝統的ではありますが、現在では洋装で祝うご家庭も多くあります。
着物は写真撮影のときだけ着て、参拝は洋服でという方法も人気です。
大切なのは、お子さまが無理なく過ごせること。そして、ご家族みなさまが安心して楽しい思い出を作れるようにすることです。
・数え年と満年齢、どちらで祝えばいい?
七五三の年齢には、昔ながらの「数え年」と、現在主流の「満年齢」があります。
数え年は生まれた年を1歳と数え、正月を迎えるたびに年齢が加わります。
一方、満年齢は誕生日ごとに1歳ずつ年をとる数え方です。
どちらを選んでも問題ありませんが、体の大きさや兄弟姉妹の年齢差によって、柔軟に考えてよいでしょう。
ご兄弟が同じ年に祝えるように調整するご家庭もあります。
七五三で気をつけたいマナーと心得|知っておきたい基本のルール
七五三は、子どもが健やかに成長してきたことへの感謝と、これからの健康を願って行う日本の伝統行事です。近年は家族ごとの考え方に合わせて自由な祝い方が広まりつつありますが、やはり知っておきたい基本の七五三のマナーもあります。

神社へのお参りの際の作法や服装、写真撮影の流れまで、事前に理解しておくことで、心を込めた思い出深い一日を過ごすことができるでしょう。
・服装とマナー
七五三では、主役となるお子さまだけでなく、付き添うご家族の服装にも気配りが必要です。
服装は和装でも洋装でも構いません。
お子さまの服装:
和装(着物・羽織袴・被布など)でも、洋装(ワンピース・スーツなど)でも問題ありません。
洋装の場合は、少し落ち着いた色の洋服や靴も一緒に選ぶと良いでしょう。
ご家族の服装:
父母ともに、フォーマルな服装が基本です。主役であるお子さまよりもやや控えめなものを選ぶのがポイントです。
ジーパンやトレーナー、サンダルなどの普段着やラフな服装は避け、品のある服を選びましょう。
和装の場合は、お子さまよりも控えめな色合いや柄にすると調和がとれます。
ご家族全体の服装の統一感も大切です。
例えば、母子が洋装で父だけが和装ではちぐはぐな印象になってしまうことも。事前に相談して、全体のバランスを見ておくと安心です。
・着物を準備するときの注意点
お子さまに和装をさせる場合、準備にはある程度の時間が必要です。
特に着物を購入または仕立てる場合は、以下の点にご注意してみてください。

着物はお子さまの体型に合わせて「肩上げ」「腰上げ」などのお直しが必要です。七五三が近づくと、着物の品ぞろえが少なくなったり、仕立てに時間がかかることがあります。かといって、早すぎると成長してサイズが合わなくなることも。成長の度合いを見て、無理のない時期に準備を始めましょう。
⏰ 目安としては、着物の予約や購入は8月〜9月頃、仕立てや受け取りは七五三の1か月前を目安にすると安心です。
・神社でのお参り・ご祈祷の作法
七五三のお参りでは、神社に対する敬意をもって行動することが大切です。以下のような基本的な作法や手順を事前に確認し、参拝当日を迎えましょう。
神社での基本的な参拝作法
鳥居をくぐる:
軽く一礼してから通る。帰るときも神前に向かって一礼する。
参道を歩く:
真ん中は神さまの通り道とされるため、端を歩くようにする。
手水(ちょうず)で清める:
右手にひしゃくを持ち、左手→右手→口をすすぎ、最後にひしゃくを立てて洗います。
お賽銭を入れる:
賽銭箱の前で軽く一礼してから、静かにお金を入れる。
拝礼(二礼二拍手一礼):
深く2回お辞儀→2回手を打つ→両手を合わせて祈り→両手を下ろしたら最後にもう一度深くお辞儀する。
神社は神聖な場所なので素足・短すぎるスカートなど、肌の露出が多い服装は控えましょう。また、ご祈祷を受ける際は、事前に神社の受付方法や初穂料、駐車場の有無などを調べておくとスムーズです。
七五三の記念写真
七五三の思い出として残しておきたいのが「写真撮影」です。七五三当日(11月15日)にする撮影や5月ごろからの前撮り撮影、七五三を過ぎてからの後撮り撮影があり、撮影のタイミングにも選択肢があります。
・撮影の時期と特徴
撮影方法特徴・良い点注意点
当日撮影
お参りや食事と一緒に済ませられる
⇒一日のスケジュールが忙しくなりがち。お子さまの集中力や疲れに注意。
前撮り
余裕をもって撮影できる。着物に慣れる練習にも◎
⇒別日に時間をとる必要がある。
後撮り
日焼け後の肌が落ち着き、予約も取りやすい
⇒年賀状などに使いたい場合は早めの撮影が必要。
・写真には「家族の姿」も残しておこう

七五三の写真は、成長したお子さまの姿だけでなく、ご家族とのつながりも感じられる大切な記録です。ごきょうだいも一緒に着物を着たり、家族全員で揃った写真を残すことで、より思い出深い一枚になります。
写真館での写真撮影のメリットは撮影用の衣装を用意しているところが多いため、和装での記念撮影は自分たちですべて準備しなくても、手軽に家族全員で着物を着ての撮影もすることが出来ます。
・お祝いのかたちはそれぞれのかたちで大丈夫
ご祈祷・参拝・食事会・撮影などを1日ですべて行うのが難しいご家庭も多くあります。
お子さまの体調やご家族の予定を考え、必要に応じて簡略化したり、日程を分けたりするのもひとつの工夫です。参拝ができなかったとしても、写真だけを残すご家庭も最近では増えて来ています。そこには、お子さまの成長を喜ぶ気持ちや、ご家族のあたたかな想いを写真と思い出として一緒に残すことができます。
アニーズスタジオの七五三撮影
アニーズスタジオはお子さまの成長を写真という形を通して記録に残すことができるスタジオ写真館です。七五三の撮影では、さまざまなサービスをご用意しております。
・和装、洋装どちらも着る事が出来る
アニーズスタジオでは古風な着物から今風の洋装まで種類豊富な衣装をご用意しておします。撮影料は変わらず、和装から洋装へお着替えを楽しむことが出来ます。また撮影料の中にお子さまのヘアセット、メイク、お着付け代も含まれているので美容院などの予約も必要なく、パパママも安心して気軽にご来店頂くことが出来ます。
他にも撮影とは別日に神社参拝を検討しているパパママには嬉しい、着物のレンタル、ヘアセット、お着付けまでアニーズスタジオですべてのお支度も可能です。
まとめ|心に残る七五三に

七五三は、形式にこだわりすぎるものではなく、「わが子の成長を祝う心」がいちばん大切です。
古くから日本に続く行事ですが時代とともに柔軟になったことで広く受け入れられるようになっています。お子さまの成長をご家族でお祝いし、気持ちの良い一日にしましょう。アニーズスタジオでは、お子さまの成長を残せる撮影環境を整えて、みなさまのご来店をお待ちしております。