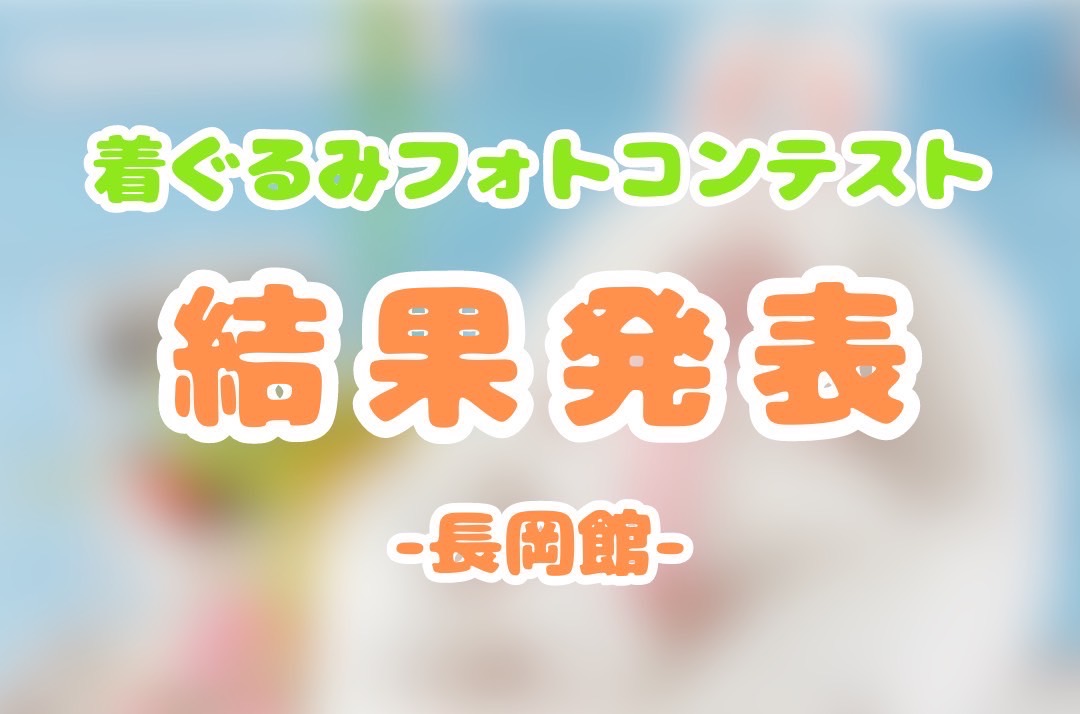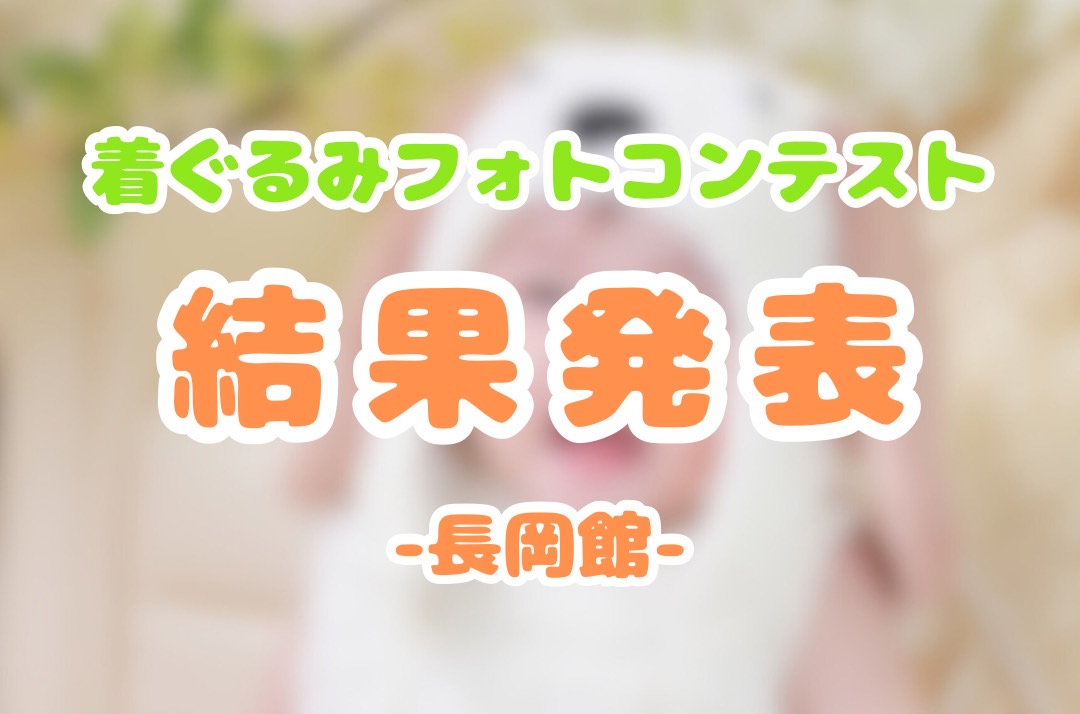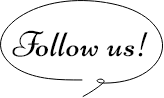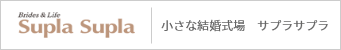赤ちゃんのイベントカレンダー

赤ちゃんのお祝いイベントカレンダー
赤ちゃんが1歳になるまでのお祝いイベント!
赤ちゃんが生まれてから1歳を迎えるまでの1年間は、家族にとってかけがえのない時間です。
日々成長する姿を間近で見守りながら、その成長を祝う数々の記念行事が日本には根付いています。
お七夜、お宮参り、お食い初め、ハーフバースデー、初節句、ファーストバースデー…
これらのイベントには、家族や親戚が赤ちゃんの成長を祝い、今後の健やかな成長を願う想いが込められています。
赤ちゃんが1歳になるまでの記念行事について、それぞれの由来や内容を詳しくご紹介します。
1. 生後何日目?で行事に悩んだら
赤ちゃんが生まれてから1歳を迎えるまでには、生まれてからの日数を基準に行われる行事が多くあります。
しかし、具体的な日数を計算するのが難しく、悩んでしまう方もいるのではないでしょうか。
❶月齢の数え方
赤ちゃんの成長や行事のタイミングを考える際、月齢や日数の数え方には2種類の方法があります。
- 【現代の数え方】
生まれた日を「生後0日目」とし、翌日を「1日目」とするのが一般的な方法です。 - 【日本古来の数え方】
生まれた日を「生後1日目」とする昔ながらの数え方です。この方法は、お七夜やお宮参りといった伝統行事において優先されるケースが多いです。
どちらの数え方を採用するかは家庭や地域の習慣によることが多いですが、伝統行事を行う場合は古来の数え方を基準にスケジュールを組むと良いでしょう。

❷行事スケジュール管理のヒント
最近では、月齢や生後何日目かを自動で計算してくれるウェブサイトや育児アプリが多く登場しています。
これらのツールを活用することで、計算ミスなく、行事の日程をスムーズに管理することができますよ。
- 【生後日数の自動計算】
出生日を入力するだけで、生後何日目かを簡単に確認できます。 - 【通知機能】
お七夜やお宮参りなどの重要な日を事前に通知してくれるアプリもあり、忙しい育児の中でスケジュール管理がしやすくなります。 - 【行事ガイド】
行事の概要や準備物について教えてくれる機能があるものもあります。
*無理のないスケジュールを心がけて!
赤ちゃんの行事は、生後すぐのタイミングで行うものも多いため、ママや赤ちゃんの体調が優れないときは無理をせず日程を調整することも大切です。
自動計算ツールやアプリを上手に利用して、家族みんなが安心してお祝いを楽しめるよう工夫してみてくださいね。
2. 生後7日|お七夜とは?
赤ちゃんが生まれて最初に迎える行事が「お七夜(おしちや)」です。
赤ちゃんの誕生を祝う日本の伝統的な行事です。
この日を迎えるにあたり、生まれた日を0日目と数える地域もあれば、1日目とする地域もあり、数え方には違いがあります。
お七夜は平安時代から続く行事とされていて、当時は栄養状態や医療が未発達だったこともあり、生後7日を無事に迎えることが難しい赤ちゃんも多くいました。
そのため、この節目を喜び、赤ちゃんの健やかな成長を願う意味で行われるようになりました。
❶お七夜の由来と風習
お七夜の由来は、赤ちゃんが無事に7日間を過ごしたことを祝い、家族の絆を深める行事として広がったものです。
この日に「命名書」を用意し、赤ちゃんの名前を披露するのが一般的で、命名書を神棚に飾る風習も続いています。
命名書は、かつては書道家に依頼して直筆で書いてもらうのが主流でしたが、現在では文房具店やネットショップで簡易なものを購入できるため、手軽に準備ができます。
赤ちゃんの名前を記録する特別なアイテムとして、思い出に残る工夫をする家庭も増えています。
❷お祝い膳と現代のお七夜のスタイル
お七夜では、お祝い膳を囲んで家族や親せきと一緒に食事をするのが伝統的なスタイルです。
祝い膳には赤飯や尾頭付きの鯛など、縁起の良い料理が並べられることが一般的でしたが、生後7日目は赤ちゃんもまだ安定していない時期で、ママも体調が回復していない場合が多いため、現在では簡略化されることもあります。
最近では、命名書の用意だけに留めたり、豪華な食事を出前やケータリングで済ませる家庭が増えています。
❸昔と今のお七夜の違い
かつては、お七夜はパパ側の祖父が主催し、親戚一同を招いて盛大に祝われることが一般的でした。
しかし、現代ではそのような大規模な祝いの形は少なくなり、家族だけでシンプルに祝うスタイルが主流です。
ママが里帰りしている場合はママの実家で行うことが多く、すでに自宅に戻っている場合はパパや兄弟とともにお祝いするなど、家族の状況に合わせて柔軟に対応されています。
❹お七夜を無理なく楽しむために
お七夜は、赤ちゃんの誕生を祝う大切な節目ですが、ママの体調や赤ちゃんの状況を最優先に考えることが大切です。
伝統的な形式にとらわれる必要はなく、できる範囲で家族と一緒に温かい時間を過ごせれば、それだけで十分です。
簡単な形式であっても、赤ちゃんの誕生を喜ぶ気持ちを込めたお祝いは、家族の絆を深める良い機会となりますね!
❺お七夜の準備と楽しみ方
お七夜の最大のイベントは、赤ちゃんの名前を命名書に書いて神棚や床の間に飾る「命名式」です。命名書は、赤ちゃんの名前を正式に記したもので、昔は特別な和紙に書かれる現代では手軽な半な紙や色紙に書くことも増えています。
一緒にお祝い膳を準備し、家族が集まって食事をしながら赤ちゃんの誕生を祝います。
また、このタイミングで赤ちゃんの手形や足形を取っておけば、家族にとって素晴らしい思い出となります。
3. ニューボーンフォト(生後3週間まで)
ニューボーンフォトは、生後3週間までの赤ちゃんの姿を写真に収める記念行事です。
もともとは海外で広く親しまれていましたが、近年日本でも人気が高まり、多くの家族が新生児期の特別な瞬間を写真に残すようになりました。
赤ちゃんのふわふわとした髪や小さな手足、柔らかな表情は、この時期にしか撮影できない貴重なものです。

❶ニューボーンフォト撮影のポイント
ニューボーンフォトは、生後2~3週間頃に撮影するのが一般的です。
この時期の赤ちゃんはまだ体が柔らかく、独特の新生児らしいポーズや表情を自然に記録できるので、理想的なタイミングとされています。
撮影場所は写真館やフォトスタジオで行われることが多いですが、産後間もない時期で外出が難しい場合は、自宅への出張撮影もおすすめです。
出張撮影では、プロのフォトグラファーが専用の撮影セットや小道具を持参してくれるため、自宅でもスタジオのような本格的な写真を撮影できます。
❷撮影テーマとスタイル
ニューボーンフォトでは、シンプルで自然なスタイルが特に人気です。
赤ちゃんの柔らかな体のラインや可愛らしさを引き立てるテーマが多く用いられます。
・ふんわりしたブランケットや花びらを背景に:優しい雰囲気の演出ができる
・ぬいぐるみや家族の記念アイテムと一緒に:家族の愛情を感じられる写真に!
・シンプルでナチュラルなスタイル:余計な装飾を省き、赤ちゃんそのものの可愛らしさを引き出します。
❸ニューボーンフォトの魅力
ニューボーンフォトは、家族や友人への贈り物としても喜ばれるほか、赤ちゃんが成長した後に振り返ると、心温まる思い出として残ります。この時期だけの特別な瞬間を写真に残すことで、家族の絆を深め、かけがえのない記念品として大切な思い出になるでしょう。
4. お宮参り(生後1ヶ月頃)
お宮参りは、赤ちゃんが生まれて初めて神社を訪れる日本の伝統的な行事です。
正式には、男の子は生後31日〜32日目、女の子は生後32日〜33日目に行うのが一般的とされています。この日を迎えることができたことを神様に感謝し、赤ちゃんの健やかな成長と健康を祈願します。

❶お宮参りの場所
お宮参りでは、神社やお寺でご祈祷を受けるのが主流です。特に、赤ちゃんが生まれた土地を守るとされる「産土神(うぶすながみ)」に祈りを捧げるため、生まれた地域にある神社を選ぶことが多いです。ただし、特定の神社でなければならないという決まりはなく、家族にとって都合の良い場所で行うこともできます。
❷お宮参りの服装
お宮参りでの赤ちゃんの正装は「祝着(のしめ)」とされています。祝着は、男の子の場合は勇ましい柄が描かれたもの、女の子の場合は華やかな柄が描かれたものが選ばれることが多いです。
最近では、明確な服装のルールに縛られることなく、ベビードレスやアフガン(おくるみ)を使用して参拝する家庭も増えています。赤ちゃんがより快適に過ごせる工夫がされています。
お参りの後には、赤ちゃんの成長をするために写真撮影を行います。 神社での撮影以外にも、写真館やスタジオで事前に記念写真を撮る方も多いです。 出張撮影も便利で、神社での様子や家族全員の写真を残せるため、お宮参りの一日を素敵な形で記録に残すことができます。
❸お宮参りの日程調整
お宮参りの日取りについては、必ずしも生後31日〜33日に行う必要はありません。赤ちゃんやママの体調を優先し、家族の都合に合わせて日程を調整することが大切です。体調に無理のないタイミングで行うことで、お祝い当日を安心して迎えることができます。
❹まとめ
お宮参りは、赤ちゃんの健やかな成長を願う家族にとって特別な行事です。伝統に基づきながらも、現代のライフスタイルに合わせた柔軟な対応が主流となっています。赤ちゃんやママの体調を最優先に考え、家族全員で素敵な思い出を作ってくださいね。
5. 生後100日|百日祝い(お食い初め)
「百日祝い(お食い初め)」は、生後100日前後に行う伝統行事で、赤ちゃんの健やかな成長を祝い、
「生涯食べ物に困ることがありませんように」と願いを込める特別なお祝いです。
❶百日祝いの由来と変化
古くからの習わしでは、赤ちゃんの父親と父方の祖父母が主導し、神社でお参りをするのが一般的でした。
また、親族を招いて盛大にお祝いする家庭も多くありました。
しかし、現代では核家族化が進む中、ママとパパ、赤ちゃんだけでシンプルにお祝いを行うスタイルが増えています。
❷お食い初めの方法
百日祝いのメインイベントである「お食い初め」では、お祝い膳を用意し、赤ちゃんに食べさせる真似をするのが特徴です。
この儀式には、まだ食べ物を口にできない赤ちゃんに対して、健康的に成長し、食に困らない人生を願う親の想いが込められています。
❸お祝い膳の準備方法
お祝い膳は、家庭で用意する場合もあれば、外部のサービスを利用することも可能です。最近では、仕出しや出前、レストランの「お祝い膳プラン」を活用する家庭も増えています。
家庭でお祝い膳を用意する際は、一汁三菜を基本とした縁起の良いメニューが一般的です。
以下が代表的な料理例です:

・尾頭付きの鯛:祝福と繁栄を象徴する定番料理。
・赤飯:赤色には厄除けの意味があり、お祝いに欠かせない一品。
・はまぐりのお吸い物:二枚貝が「良縁」や「調和」を象徴。
・香の物:漬物など、食卓を彩る一品。
これらの料理は、地域や家庭の文化によって多少異なる場合があります
また、「丈夫な歯が早く生えますように」との願いを込めて、「歯固めの石」を用意し、祝い箸でその石に触れさせる「歯固めの儀式」を行います。この儀式には、赤ちゃんが生涯にわたり健康な歯を持ち、食べ物に困らないようにとの思いが込められています。
❹お食い初め膳の特徴
祝い膳には、赤ちゃんの性別に応じた器を用意するのが一般的です。
・男の子:朱塗りの漆器
・女の子:外側が黒、内側が朱色の漆器
このように、器の色やデザインにも伝統的なこだわりがあり、祝い膳を華やかに演出します。
❺現代のお食い初めのスタイル
忙しい日常の中で、家庭での準備が難しい場合には、専門店のサービスを利用するのも良い選択肢です。
また、写真撮影を含めてプランにしているレストランや写真館も多く、家族で思い出を作りながらお祝いすることができます。
❻まとめ
百日祝い(お食い初め)は、赤ちゃんの成長を喜び、家族の絆を深める大切な行事です。
伝統を尊重しつつ、現代のライフスタイルに合った形で行うことができます。
無理のない方法で、赤ちゃんの幸せを願う素敵なお祝いの時間をお過ごしくださいね。
6. ハーフバースデー(生後6ヶ月)
「ハーフバースデー」は、生後6カ月を祝う比較的新しい行事で、近年お祝いするご家庭が増えています。お七夜やお宮参りのような古くからの伝統行事ではないため、特定の形式や決まりはありません。
そのため、一般的なお誕生日祝いと同じ感覚で自由に楽しむことができます。
赤ちゃんの成長を振り返りながら、1歳の誕生日までの時間をさらに楽しむきっかけになります。自由なスタイルで思い出に残るお祝いをしてみてはいかがでしょうか。

❶ハーフバースデーの魅力
赤ちゃんの成長は驚くほど早く、6カ月と1歳では見た目や行動に大きな違いがあります。
そのため、この節目に成長を記録するご家庭が増えています。
特にフォトスタジオで記念写真を撮影するのは人気のひとつです。
スタジオでは、赤ちゃん専用の可愛い衣装や小道具を使って撮影できるため、思い出深い一枚を残すことができます。
また、生後6カ月ごろは離乳食が始まる時期でもあるため、離乳食を使った「離乳食ケーキ」を用意してお祝いするのも人気です。
赤ちゃんが安心して食べられる食材で作ったケーキは、家族での楽しい食卓を彩るアイデアとして人気を集めています。
❷ハーフバースデーの楽しみ方
ハーフバースデーは形式にとらわれず、家族のスタイルに合わせてお祝いできる自由なイベントです。以下は、よく取り入れられるアイデアです。
・記念写真撮影:フォトスタジオや自宅で撮影を行い、6カ月の姿を記録。
・飾り付け:バルーンやガーランドを使ったデコレーション。
・家族でのお祝い:離乳食ケーキやお祝いメニューを用意して家族で楽しむ。
7. 初節句(桃の節句・端午の節句)
「初節句」は、女の子が初めて迎える桃の節句(3月3日)、男の子が初めて迎える端午の節句(5月5日)
を祝う伝統行事です。
この行事では、赤ちゃんの健やかな成長を願い、それぞれの節句にちなんだ飾りや料理でお祝いします。
赤ちゃんがまだ1~2カ月程度のときに初節句を迎える場合、翌年に改めてお祝いをする家庭もあります。
産後のママの体調や、他の行事との兼ね合いを考慮して無理なく行うことが大切です。
❶桃の節句(3月3日)
女の子の初節句にあたる桃の節句では、ひな人形を飾るのが一般的です。
ひな人形には、無病息災や健やかな成長、美しい女性へと成長する願いが込められています。
お祝い膳としての定番は
・ちらし寿司:華やかな見た目でお祝いにぴったり。
・ひし餅:紅白緑の3色に込められた健康と幸福への願い。
・ひなあられ:五穀豊穣や厄除けを意味するカラフルなお菓子。
❷端午の節句(5月5日)
男の子の初節句にあたる端午の節句では、五月人形やこいのぼりを飾ります。
五月人形には厄除けや勇敢に成長する願いが、こいのぼりには出世と成功を願う意味が込められています。
お祝いの食卓には、以下の料理が定番とされています:
・かしわ餅:柏の葉は「子孫繁栄」を象徴し、縁起が良いとされています。
・ちまき:邪気を払うとされる行事食。
・うなぎ料理やブリ料理:出世魚として有名で、力強い成長への願いを込めます。
❸初節句の楽しみ方
初節句は、家族で赤ちゃんの健やかな成長を願い、伝統を楽しむ素晴らしい機会です。
赤ちゃんを中心に、家族で写真撮影をしたり、親戚とともにお祝い膳を囲むことで、特別な思い出を作ることができます。
どちらの節句も、赤ちゃんの健康や成長を願う深い意味を持つ行事です。
それぞれの伝統に沿った飾り付けや料理を楽しみながら、大切な節目を温かい気持ちでお祝いしてください。
8. 1歳の誕生日
赤ちゃんがいよいよ1歳を迎える「初誕生日」は、ママや家族にとっても特別な節目のお祝いです。産後1年という記念すべき日を盛大に祝うため、多くの家庭では赤ちゃん用のケーキやごちそうを準備してお祝いを楽しみます。この時期、多くの赤ちゃんは離乳食が進んでいるため、特別なメニューでお祝いの食卓を彩ることができます。

❶初誕生日の伝統行事
初誕生日には、「一升餅」や「選び取り」といった伝統的なイベントが行われることが多いです。これらの行事には、赤ちゃんの将来への願いが込められています。
- 【一升餅】
一升(約2kg)の餅を赤ちゃんに背負わせる、一生食べ物に困らないようにとの願いが込められたお祝いです。一升餅のイベントには地域や家庭によってさまざまなスタイルがあります。
・背負わせる:餅を背中に背負わせて、力強い成長を願います。
・踏ませる:餅を足で踏ませ、地に足をつけてしっかり歩む人生を祈願。
・転ばせる:わざと赤ちゃんを転ばせ、困難を乗り越える力を象徴的に示す場合もあります。 - 【選び取り】
赤ちゃんの前にいくつかの道具を並べ、赤ちゃんが最初に手に取ったもので将来の職業や性格を占うイベントです。用意する道具やその解釈は地域や家庭によって異なりますが、以下は一般的な例です:
・電卓やそろばん:商売やビジネスの才能。
・本:学者や研究者になる。
・お金:経済的に裕福になる。
・定規:計画性や几帳面さを象徴。
赤ちゃんが選んだものに家族で歓声を上げたり、その道具にまつわる未来のエピソードを語り合ったりすることで、思い出に残る楽しい時間を過ごせます。❷初誕生日を楽しむアイデア
・記念写真撮影:特別な衣装やデコレーションを用意し、成長を記録する一枚を残しましょう。
・スマッシュケーキ:赤ちゃんが手づかみで食べる専用のケーキで、初めての食体験を楽しむ家庭も増えています。
・家族での会食:赤ちゃんが主役となる食卓を囲み、家族みんなで笑顔あふれる時間を過ごしましょう。
❸まとめ
初めての誕生日は、赤ちゃんの健やかな成長を祝うだけでなく、これまで育児に励んできたママやパパにとっても記念すべき日です。伝統行事を取り入れることで、家族の絆を深め、思い出に残る素敵な一日となることでしょう。赤ちゃんの未来を願いながら、楽しいお祝いをお過ごしください!
9. 年中行事や月齢フォトも大切な思い出作り
赤ちゃんが1歳になるまでには、節目となるお祝いイベントだけでなく、年中行事や月齢フォトも大切な記念のひとつです。ここでは、それ以外のおすすめの記念行事や撮影アイデアをご紹介します!
❶初正月
赤ちゃんが初めて迎えるお正月も、家族にとって大切な行事のひとつです。この時期は親戚が集まり、赤ちゃんを初めて披露する絶好の機会にもなります。遠方の親戚やいとこたちと初めて対面する赤ちゃんにとっても、家族の絆を深める大切な時間です。
また、初めてのお正月には、赤ちゃんや家族の写真を使った年賀状を作成するのもおすすめです。これを機会に、普段なかなか会えない友人や親戚にも赤ちゃんの成長を報告することができます。
❷月齢フォトや寝相アート
赤ちゃんの成長記録として、最近人気を集めているのが「月齢フォト」です。毎月の成長を記録することで、赤ちゃんがどのように変化していったのかを振り返ることができます。
毎月同じアイテムや背景を使って写真を撮ることで、赤ちゃんの成長の過程をわかりやすく残すことができます。
❸月齢フォトのポイント
・数字で月齢を表現:オムツや数字のブロック、ステッカーなどを使い、生後何ヶ月かを示します。
・同じアイテムを使って撮影:ぬいぐるみや背景を毎月統一することで、成長の変化がわかりやすくなります。
・日常の特別な瞬間も記録:初めての寝返りや離乳食を食べた瞬間など、節目の出来事もフォトに収めると良い思い出になります。
月齢フォトは自宅で気軽に撮影できるため、外出が難しい産後の時期でも楽しめる記念行事です。赤ちゃんの可愛さを写真にたくさん残しておけば、家族で振り返る際に話が弾みます。
❹手形・足形アート
赤ちゃんの小さな手や足は、新生児期から少しずつ大きく成長していきます。その愛らしいサイズ感を記録に残す方法として、「手形・足形アート」が人気を集めています。赤ちゃんが成長した後も、このアートは思い出として家族の宝物になるでしょう。
・成長の記録:赤ちゃんの手や足がどれほど小さかったかを実感でき、成長を振り返ることができます。
・家族の絆を深める:制作を通して家族で楽しみながら、絆を感じるひとときとなります。
・インテリアとして飾れる:アートとして仕上げることで、家族の思い出を日常の一部にすることができます。
まとめ

赤ちゃんの成長をお祝いするさまざまなイベントをご紹介しました。
1歳までにこれほど多くの記念行事があることに驚かれる方もいるのではないでしょうか?
これらの行事には、古くから赤ちゃんの健やかな成長を願う家族の温かい気持ちが込められています。
ただ、すべてのお祝いを完璧に行う必要はありません。
赤ちゃんや産後のママの体調を最優先に考え、乳児検診や予防接種のスケジュールも含め、無理のない範囲で楽しむことが大切です。
最近では、ママの負担を軽減するための便利なお祝いグッズやサービスも豊富に登場しています。
こうしたツールを上手に活用しながら、大切なイベントを家族みんなで楽しい思い出にしてくださいね!
撮影のご予約・ご見学ご希望の際は→コチラ
LINEでのご予約はコチラ↓